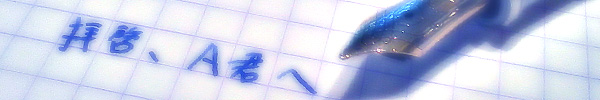
【A君と僕〜雰囲気的な5つの詞(ことば):幸】
01.君が笑うから
昼休みや放課後を過ごすのは、いつも図書室の窓際のテーブルでと決まっている。クラスメイト達は校庭で遊んだり教室でつまらない事を喋ったりしているけど、僕にはそんな暇なんて無い。遊んでいられる余裕があるなら、少しでも多く勉強しなければならない。
いつも独りでいる僕の目の前に突然、彼が現れた。
「三星(みつぼし)ってこんなとこいたんだ。いつも昼休み教室いねぇな、って思ってたけど」
まさか僕の勉強を邪魔する気なんだろうか、と警戒したけれど、彼は僕の斜め向かいの席に座ると手にしていた本を読み始めた。横目でちらりと表紙を確認したところ、古いけれど今でも人気のある娯楽小説だった。
彼は殆ど毎日図書館に現れるようになった。彼は決まって僕の斜め向かいに座る。僕が座る席を替えてみても意味は無かった。
僕は他人の気配に苛立ち、ついに彼に苦情を言おうと顔を上げた。
彼は小説を読みながら楽しそうに笑っていた。
その笑顔に毒気を抜かれた僕は、再び視線を参考書に落とした。
それ以来、僕が彼の存在に苛立つことは無い。
02.今はただどうしようもなく
「三星って何でそんなに勉強してんの。志望校どこ?」
「樫ヶ谷学院」
じゃあ仕方ねぇな、と呟き、彼は読書に戻った。感想文の宿題があるからだろう、今日はいつもの娯楽小説ではなく課題図書を読んでいる。
前髪で彼の表情が隠れ、僕は嫌な事を思い出す。
この前、職員室で彼の弟が志望校に樫ヶ谷を奨められている現場を見てしまった。
僕がどんなに勉強しても勝てたためしがない相手は、先生からお前なら絶対に受かる、と言われていた。僕はそんな言葉を貰った事なんて一度も無い。
なのに彼の弟は、俺は惣稜しか受けませんから、ときっぱりと拒絶した。
彼が何も言わなかったのは、もしかして気を遣ってくれたんだろうか。
悔しいと思う反面、嬉しくも思う。
とにかく今は受験勉強に集中しよう。僕は絶対に樫ヶ谷の高等部に合格しなければならないのだ。
――今度こそ、母さんと僕の幸せを掴むためには。
03.どうかお幸せに
受験から解放されて初めて登校した日、僕はまっすぐに彼の席に向かった。
「合格、したよ」
僕から彼に声をかけたのは、実はこれが初めてだった。図書室以外で話をするのも。
「凄ぇじゃん! 良かったな三星」
挨拶も無しにいきなり報告、だった事を言った後に気付いたけれど、彼は笑顔で僕の合格を喜んでくれた。
「そっちは?」
「俺も受かった」
受験直前はお互いに、もう駄目かもと何度も独り言を呟いた。だからお互い、相手の高校合格が自分の事のように嬉しく感じるのだろう。
そして喜び合う相手は、お互いしかいない。友達と遊ぶ暇より勉強をする時間を取った僕と、友達と言う存在に興味を持たなかった彼と。
「俺達、四月から高校生なんだな」
最近中学生になったばっかな気がする、と彼は目を細めた。
「高校行っても元気でね」
願わくば、彼は彼なりに幸せな高校生活を送って欲しい、と思う。
「三星もな……って、まだ卒業式まで時間あるじゃん。お前気が早すぎ」
彼は僕の髪をくしゃりと撫で、苦笑した。
04.それは安らぎにも似た
高校合格から卒業までの短い間も、僕の図書館通いは変わらなかった。合格発表の時に購入した教科書や高校の参考書を持ち込んで勉強している。
彼もまた、僕の斜め向かいで毎日のように娯楽小説を読んでいた。卒業までに、最初に読んでいた本の作者が書いた別の作品も全て制覇するのが目標のようだ。
白状すると、お互い第一志望に合格したことを伝えあった日の昼休み、彼が図書室に現れたのを見て僕は凄くほっとしてしまった。
お互い言うのは「独り言」で、相手に干渉することは殆ど無い。けれどいつの間にか僕にとって、図書室にいる彼は日常の風景の一部になっていたのだ。
僕は数学の問題を解く手を止め、彼の動作が生み出す気配を全身で感じ取ろうとした。
小説のページがめくられる音が左耳から入ってくる。それはとても心地よくて、僕は予定より五分も長く勉強を中断してしまった。
05.しあわせのあとさき
僕は今、樫ヶ谷学院の正門前に立っている。
学校名にぴったりの、濃い焦げ茶の布地に暗緑色のラインが入った学生服は、僕がずっと憧れてやまなかったものだ。自分で自分の服装を眺めても、未だ夢を見ているような気分が、少し残っている。
今日は入寮日。明日の入学式を経て僕は正式に樫ヶ谷学院の生徒になるのだ。
ここの図書館を利用するのが楽しみだ。外観は受験の時に見たけれど、白い壁に緑の丸屋根が映える綺麗な洋館だった。窓は大きく日当たりも良さそうだ。彼もきっと気に入るだろう――そこまで考えて、僕はもう彼と遇う事は無いのだ、と言う事実を思い出した。
途端に、寂寥が僕を苛む。
何で今更気付いてしまったんだろう。
僕と彼はただのクラスメイト同士で、図書室の同じテーブルの席に座っていただけで、友達と呼べる間柄では決してなかった。けれど彼と過ごした時間は、僕が思っていたよりも遙かに大切なものだったのだ。
彼を思い出すたび、僕は感じる。
あの頃の、初恋にも似た幸せな想いを。
(2006/12/28)
web拍手のお礼として一時期先行公開していた「拝啓、A君へ」の序章です。参の中学校時代の話。